ブログ案内人のアンデルです。
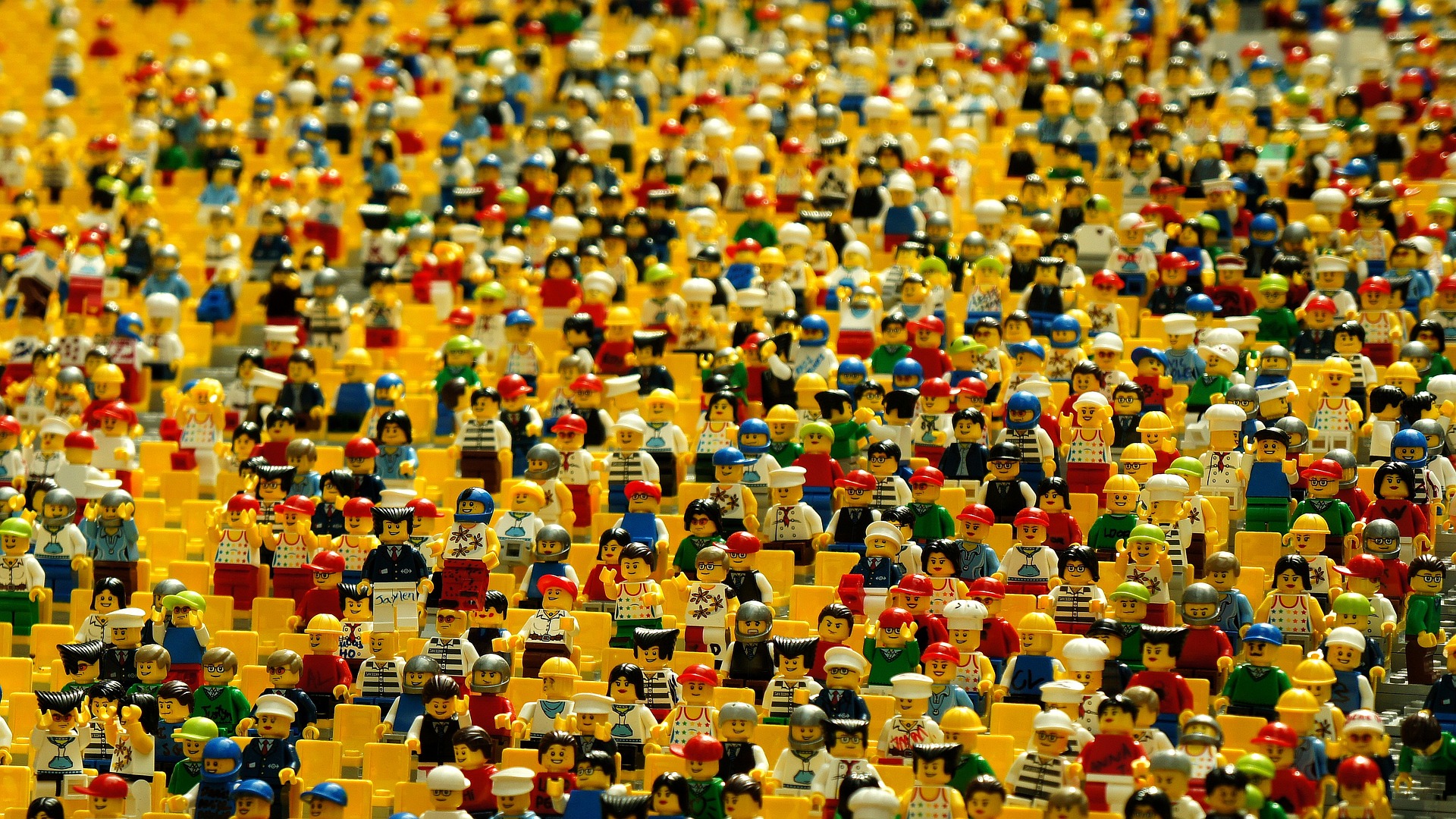
ブログ案内人のアンデルです。突然ですが、皆様は受動意識仮説という説をご存じでしょうか?「心は幻想である」という衝撃的な説なので、批判を通り越して、反感を持ってしまう方が多く、現在のところ、普及するには至っていない説です。私は、以前からこの説に非常に興味を持っておりましたので、何故、地動説と...
「何故、受動意識仮説は受け入れられなかったのか?」
という疑問に対する私なりの結論は上記事に書きました。
よかったらご覧になってください。
今回はその続編ということで、
受動意識仮説は実感できるのか?について、
受動意識仮説と共通点を持つ他の理論について、
また、最後には新仮説
「意識時間認識機能仮説」
について書いてみたいと思います。

ところで、
受動意識仮説を知ってしまった人の反応は
「むなしい」と感じる方「気が楽になった」と感じる方
「受け入れずに反論し続ける」方の三通りに分かれるそうですが、
私は納得して「気が楽になった」タイプの一人です。
・・・『心』とは正に私自身であり、私の全てを司る司令塔のような存在である・・・
と信じたくても
・・・歩く時に、私の『意識』は「左手を前に出しながら右足も前に出せ」
などと身体に命令を出したりはしない。車を運転する時の複雑な操作もしかり、
能動的に指示している感覚はない。
また、睡眠時の呼吸も『心』あるいは『意識』が身体に命令している感覚はない。
「それらは下意識や副交感神経の働きによるものである」
というのが答えであるなら、さて『心』の持つ役割とは一体何だろう?・・・
と、次々疑問が湧いてきます。
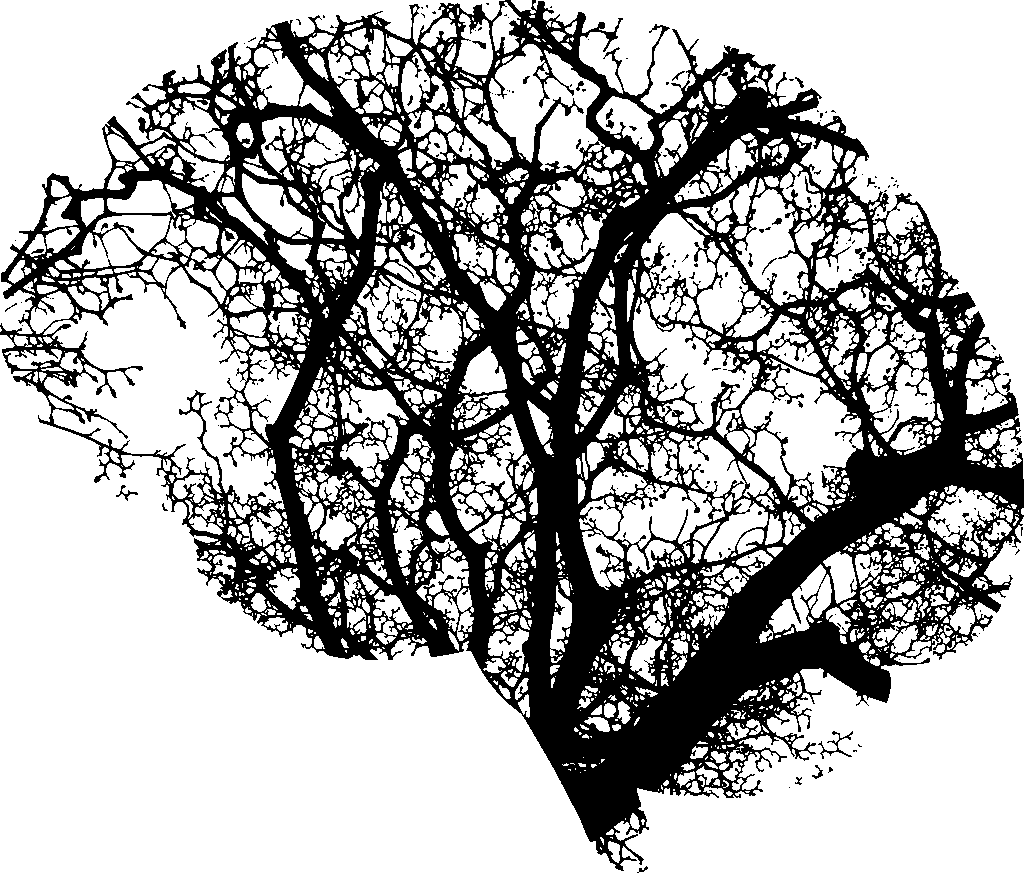
そして、疑問の答えを探すうちに
「司令塔のような存在」だったはずの『心』は、
絶対的主役の座から立ち上がり
「いやいや、そうはいっても『心』が方向性を決めるからこそ、
他の機能に役割を分担できるのだ」
と、言い訳をしながら少しづつ消極的主役へと変化し、
最終的には、最新の様々な実験結果によって
主役の座から転落してしまいます。

受動意識仮説によれば
『心』は自身を社長だと勘違いしている社史編纂室長。
「全てを司る司令塔のような存在」どころか
「出来事を記録するだけの傍観者」に過ぎないということです。
受動意識仮説は、
切り口が斬新でインパクトが強く、
完全に新しい考え方のようにも思えますが、
実は似たような思想を探すことのできる、
昔から続くテーマの答えの一つとも言えます。

ですので、
少し視野を広げてみると、
受動意識仮説は東洋的思想との
親和性が高い説だと思えるのですが、
いきなり科学的な切り口から『心』の機能を凝視してしまうと、
「心は幻想である」という刺激的な見出しの効果も相まって、
従来の考え方を覆されたと感じる方、
また、
受動意識仮説的な『心』の在り方を
「むなしい」と感じる方も多いようです。
私にもそのお気持ちは理解できます。
そして、
もしかすると、この「むなしさ」が原因で、
受動意識仮説は受け入れ難いのかもしれません。
ところで、
もし受動意識仮説の示す『心』の機能について、
我々の日常生活においても思い当たる実感があり、
よく考えてみると「普通のことだった」としたならどうでしょうか?
もしかすると、受動意識仮説に対するネガティブなイメージが変化し、
「むなしさ」が和らぐかもしれません。
そこで、
「受動意識仮説を実感できるのか?」について
考えてみたいと思います。
私事で恐縮なのですが、
これまでの人生を思い起こしてみると、
スポーツ競技、あるいは各種試験において
・・・『心』あるいは『意識』の介入度合いを低くすればするほど上手くいく・・・
という実感がありました。
特にスポーツにおいてはそうです。
そして、
この経験がそれほど特殊な経験とは思えません。
「無我夢中になり、頭の中がカラッポな時ほど素晴らしいプレーができる」
おそらく、大勢の方が経験している感覚だと思います。

社会生活を営む上で
『心』や『意識』の存在が必要不可欠と思える場面もありますが、
顔を出して欲しくない場面もあります。
特にスポーツにおいては、
競技テクニックを磨くことと同レベルで
『心』や『意識』のコントロールが大切だということは、
衆口一致するところです。
上記については、
メンタルトレーニング理論として一世風靡した、
ティモシー・ガルウェイ氏による著書「インナーゲーム」に詳しく記されています。

・・・『心』や『意識』はプレー中の集中力を妨げる存在である。
故に、それを「いかにして黙らせるか?」が成功の鍵である・・・
つまり、インナーゲーム理論によれば
『心』や『意識』は邪魔な存在なのです。
一般的にはプレーを司る主役と感じる『心』や『意識』ですが、
邪魔者扱いされているところに受動意識仮説との共通点を感じます。
一見すると非常識な理論にも感じられますが、
オリンピック競技などの実戦においても
素晴らしい効果を発揮した信頼性の高い理論です。
プレーヤーの状態を考えるとき、
『無意識』のプレーと『意識』の介入したプレーとでは
集中のレベルに雲泥の差があります。
・・・『意識』が介入しない状態こそが最も理想的・・・
とインナーゲーム理論は示しています。
以上のように、
受動意識仮説の示す『心』や『意識』と
インナーゲーム理論の示す『心』や『意識』の機能は
とても良く似ています。
受動意識仮説において傍観者とされる『心』や『意識』ですが、
インナーゲーム理論においても傍観者であることを求められています。
何故なら、本来傍観者である『心』や『意識』が
あたかも主役であるかのように振る舞い始めると、
プレーヤーは途端に集中力を欠いた状態に陥ってしまうからです。
という訳で、
インナーゲーム理論と集中力をキーワードに紐解けば、
一見難解で、遠い世界の出来事のように感じる受動意識仮説も、
実は、私達にとって既に経験済みの
普通の出来事として捉えることができます。
「無心」「無我の境地」「禅の精神」などの
私達にとってなじみのある言葉や考え方から紐解けば、
受動意識仮説の示す『心』や『意識』の機能についても
受け入れやすいかもしれません。

さて、
こうして『意識』と『集中力』の関係を手がかりに
受動意識仮説とインナーゲーム理論を比較しているうちに
『心』とは何か?の輪郭がボンヤリ見えたような気がします。
受動意識仮説によれば
・・・『意識』の役割とは、エピソード記憶をつくるためにある・・・
とされています。
エピソード記憶をつくろうとすれば、
出来事を時間軸に沿って整理する能力が求められます。
また、インナーゲーム理論によれば
・・・『意識』は過去の失敗を思い出し、未来の失敗を恐れ、
現在成すべきプレーを妨げる・・・
とされています。
こうして受動意識仮説とインナーゲーム理論が示す
2つの『意識』を並べてみると
『意識』とは、時間と深く関わる機能
であることが分かります。
これは非常に興味深いことです。
進化の過程で『心』や『意識』が発達し、
エピソード記憶が可能になった訳ですが、
インナーゲーム理論の示す『意識』の機能とは、
集中力を分散する力。
集中力とは、現在成すべきことを成す力ですので、
言い方を変えれば過去や未来を遮断する力です。
つまり『意識』とは
人が本来持つ動物的集中力を分散させる力であり、
その力によって、現在だけに集中するのではなく、
過去を振り返り未来を予測することが可能になった。
それが出来事を時間軸に沿って整理する能力、
エピソード記憶をつくる能力だと考えることができます。
また、以上のように『心』や『意識』が発達することで、
過去や未来という概念を手に入れた、と仮定すると
『心』や『意識』の進化論的役割が
・・・過去の経験から学び、未来の失敗を回避する機能・・・
と考えられます。
『心』や『意識』があるから
『時間』という概念を持つことができる。
あるいは『時間』という概念を作り出しているのは
『心』や『意識』なのかもしれません。
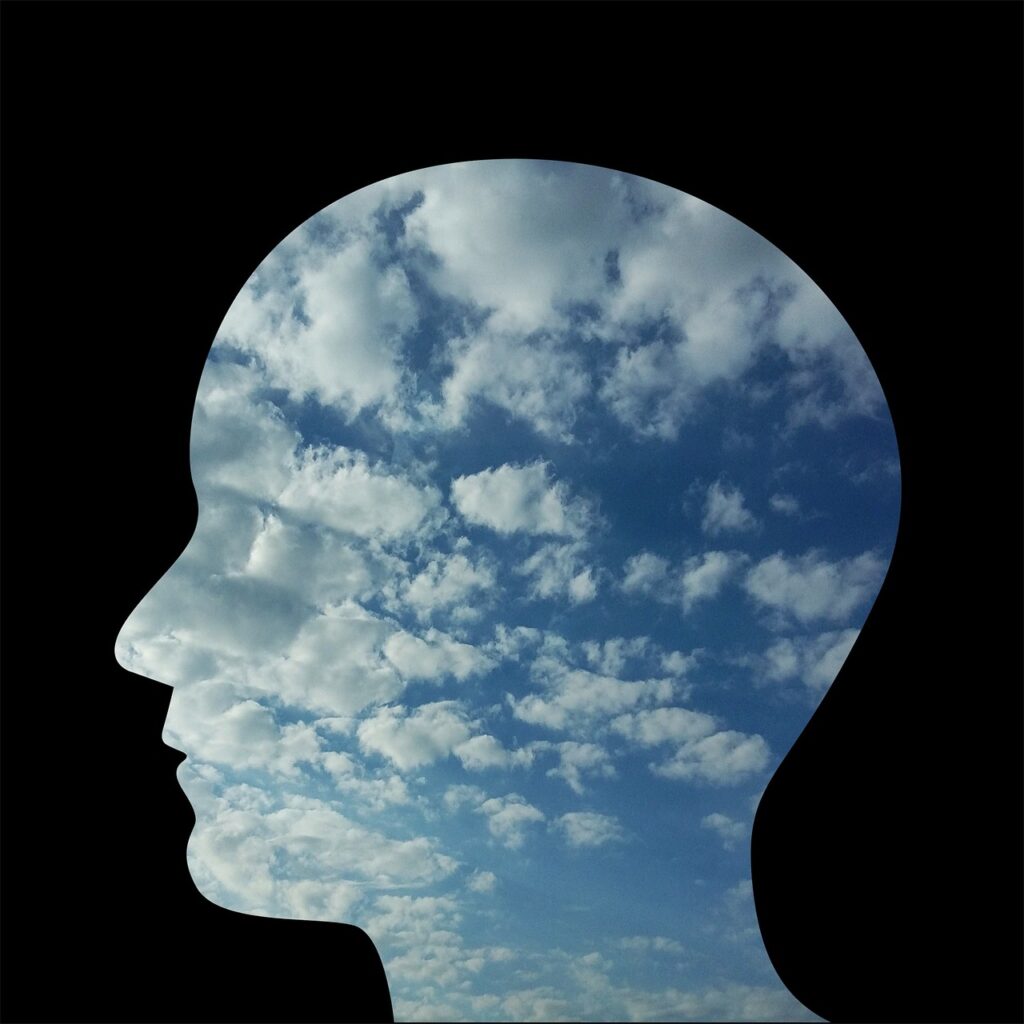
という訳で、
仮説を綴るアンデルのブログらしく
『心』や『意識』とは、時間という概念を作る為にある。
という仮説「意識時間認識機能仮説」と唱えたいと思います。
アンデル
コメント